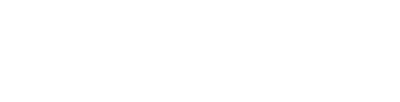ニュース&レポート
ウッドソリューション・ネットワーク 特別対談 企業活動における木材利用の意義 東京海上日動火災保険株式会社 相談役 隅 修三 氏・ナイス株式会社 取締役会長 杉田 理之
東京海上日動火災保険株式会社では、世界最大規模の木材使用量を誇る新・本店ビルの建築プロジェクトが進められています。このたび、木材利用拡大に向けた各種課題解決を図る「ウッドソリューション・ネットワーク※」は、同社相談役の隅修三氏と同ネットワークの副会長を務めるナイス株式会社取締役会長杉田理之との特別対談を昨年10月に実施し、プロジェクトの背景や目的に加え、日本の森林林業に関する意見交換がなされました。

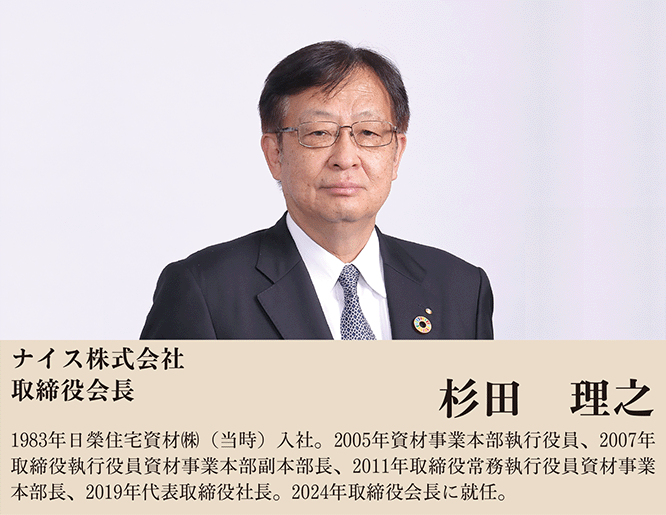
東京海上グループ新・本店ビルの建設について
国産材の需要創造で地方創生を目指す
杉田 御社が手掛ける新・本店ビルの建設プロジェクトは、国産材をできる限り多く使用することが目指されています(図1)。それにはどういった背景があるのでしょうか。
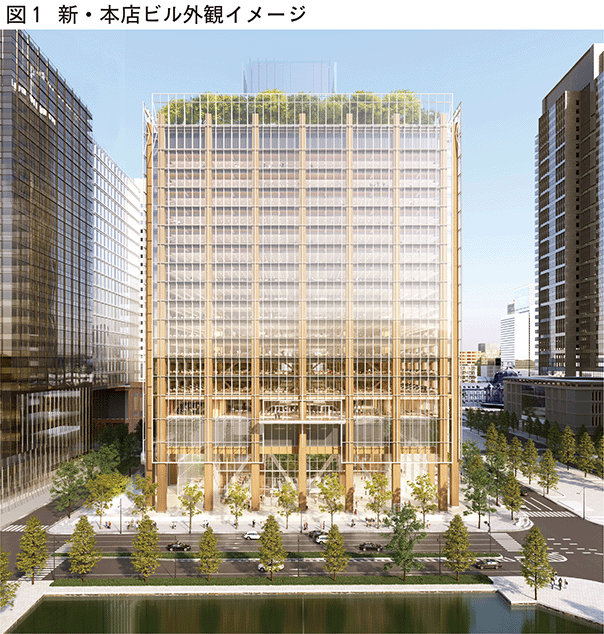
隅 日本社会の展望を考えた時に、「地方が健全でない国家は健全な国家足りえない」という想いを以前から抱いていました。2013年に当社取締役会長に就任してからは、当社に「地方創生室」を設置するなど、地方創生への貢献に繋がる各種取り組みを全国の自治体等と連携しながら行ってきました。
そうした中で目の当たりにしたのが、林業の実態です。国土の約7割を占める森林資源が、各地で適切に整備されずに荒廃していく姿は、木に囲まれて育った私にとって心が痛むものでした。そこで、林業において若者の仕事を生み出し、活性化させることが、地方創生の一助につながるのではないかと考えました。これが、新・本店ビルの建設プロジェクトの原点です。
杉田 具体的にどのような取り組みによって林業の活性化を目指されたのでしょうか。
隅 全国の林業従事者、建設業者、自治体職員からは、林業は「補助金なしでは成り立たない産業だ」という声が聞かれました。急峻な山での伐採の難しさ、働き手の不足、輸入材との価格差など、供給側の課題ばかりが目立つ中、大切なのは需要を創り出す発想だと感じていました。そこで、林業の活性化に繋がる大きな需要をどのように生み出すかを模索する中で、住宅や低層建築の木材需要には限界があると感じて悩んでいた時、欧米を中心に中高層のオフィスビルや商業施設の柱や壁、床として普及し始めていたCLT(直行集成材)に出会いました。CLTを活用すれば、中高層建築をはじめ、国産材の新たな需要を生み出せるのではないかと考えました。
2018年には、(公社)経済同友会の地方創生委員長として「地方創生に向けた"需要サイドからの"林業改革~日本の中高層ビルを木造建築に!~」という政策提言を発表し、商業・オフィスビルなどへの国産材の積極的な利用を呼びかけました。当初はデベロッパーや建築士などの関係事業者からあまり理解を得られず、メディアにもほとんど取り上げられることもない、まさに四面楚歌のような状態でした。しかし、その後も数年間にわたって木造の有用性を訴え続けた結果、賛同してくれる方が次第に増えていきました。また、昨今のカーボンニュートラルに向けた取り組みや花粉発生源対策などの政府の後押しもあり、木造ビルの注目度はますます高まってきました。
そんな中、当社の本店ビルも建て替えの時期が迫っていました。そこで、国産材の需要拡大に貢献すべく、木をできるだけ多く使用してビルを建て替える本プロジェクトの実施を、経営陣が勇気を持って決断してくれました。
木の使用量は世界最大規模
杉田 新・本店ビルはどのようなコンセプトで設計が進められているのでしょうか。
隅 1974年に竣工した赤煉瓦色のビルは多くの人から愛着を持たれていたため、建て替える上では、明確なコンセプトが必要でした。そこで、近年高層ビルが次々と建設されていますが、高さは競わずに内容・質を重視することに加え、丸の内の美しい街並みに調和し、日本の玄関口である東京駅と皇居を結ぶ行幸通りに相応しい、洗練された気品のあるデザインが必要だと考えました。そして、最高レベルの災害対応力と新しい働き方や多様性に対応できる柔軟性を備えた上で、木材をふんだんに使うことで木材需要の創出に貢献したいと考えました。これらを新・本店ビルのコンセプトとして、国内外を問わず、当社グループの社員がそこで働きたいと思い、OBやOGの方々も誇りを持てるような品格のあるビルの建築を目指しています。
杉田 完成イメージについて教えてください。
隅 新・本店ビルの大きさは、幅が約84m×84m、高さが約100mです。旧本店ビルと比較すると横幅が広くなっているほか、同じ高さで階数を25階建てから20階建てにすることで、各フロアの天井高を高くしています。そして、他にない大きな特徴として、構造材に木材を使用しています。柱には耐火集成材を用いて、地上から30mの低層部は鉄骨柱を木材で覆い、30m~100mの高層部は木柱とするほか、床の構造材や天井にはCLTを使用します(図2)。これにより、オフィスフロアには木材の質感があふれ、柔らかく和やかな空間が創り出されます。そのほか、約4,000㎡の屋上にはできるだけ木や植物を植え、都心の喧騒にありながら、人々にひと時の静寂や憩いをもたらす緑豊かな庭園を計画するなど、可能な限り多くの木材を使用する予定となっています。加えて、各フロアを内階段で繋ぐことで開放感を高めながら社内コミュニケーションを促進するといった工夫も施し、コンセプトに沿った設計としています。なお、これらの新・本店ビルのデザインは、今回のプロジェクトの意義について深く共感いただいた、世界的な建築家であるレンゾ・ピアノ氏が主宰する設計事務所、Renzo Piano Building Workshopに担当いただきました。
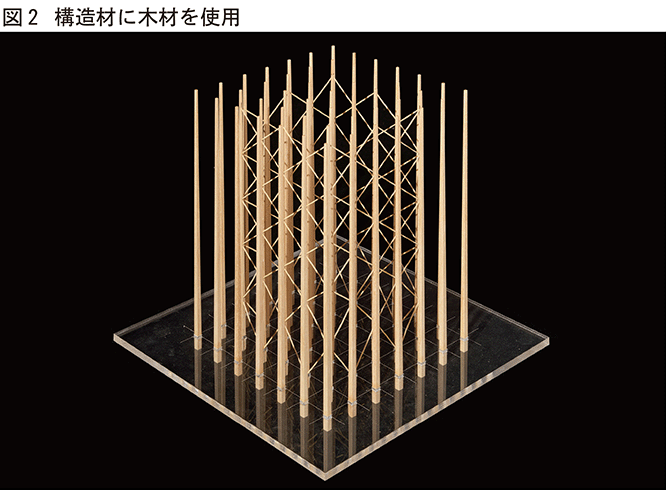
杉田 竣工される新・本店ビルが、今後どのような役割を担うことを期待しますか。
隅 これほど巨大な木造主体のビルの建築にあたっては、技術面で前例のないことが多く、建築基準法や消防法における規制との戦いが日々続いてきています。今回のチャレンジが、日本の建築業界にとって大きな転換点になると思います。
また、本プロジェクトの本来の目的は、奇をてらった木造ビルを建てることではありません。完成した新・本店ビルを見た全ての人々が、木造でこれだけ素晴らしい建築物ができるということを実感することで、ビルの新築や建て替えに木造の選択肢が生まれ、日本の中高層ビルが木造に変わっていく大きなきっかけとなることを目指しています。そして、国産材の大きな需要創造の先駆けとなり、林業再生及び地方創生に少しでも繋がることを期待しています。
森林林業と木材利用の現状と今後
森林資源の循環は山元への利益還元が不可欠
杉田 新・本店ビルの建設プロジェクトのように、需要側に木材の良さを理解いただき、新たな木材需要が創出されることは、森林・林業の循環型社会の実現において非常に重要だと考えています。森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物供給などの多面的機能を有しており、「伐って、使って、植えて、育てる」といった森林資源の循環利用を推進することで、それらの機能が持続的に維持されます。
日本における最新の国家森林資源調査によると、現在の森林蓄積は約86億㎥で、毎年1億㎥増加していると推計されています。加えて、森林の4割程度に相当する人工林は終戦直後や高度経済成長期に造林されたものが多く、そのうち約6割が50年生を超えており、利用期を迎えています。この豊富な資源を有効活用すると同時に、循環利用に向けて計画的に再造林することが必要ですが、主伐面積と人工造林面積の推移を見ると、再造林率は約4割程度にとどまっていることがわかります(図3)。少なくとも7~8割程度にまで進まなければ、将来を見据えた循環型の森林の維持は難しいと考えています。
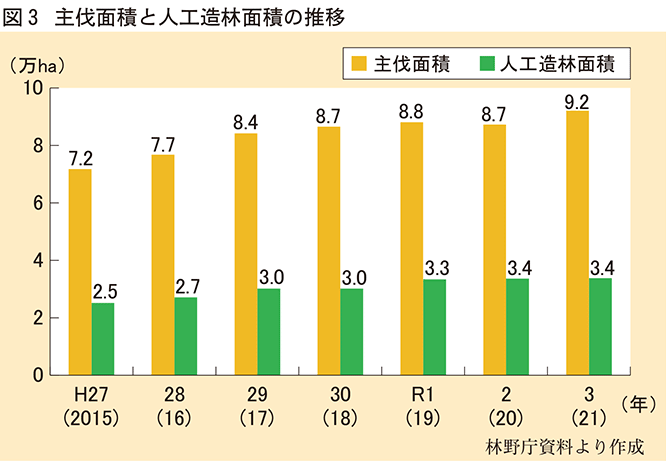
隅 山元に資金が還流する仕組みがない限り、再造林は今後も進んでいかないのではと思っています。そうした仕組みを構築するためには、どのようなことが必要になるとお考えでしょうか。
杉田 おっしゃる通り、森林整備は当然コストがかかります。再造林や育林に必要なコストを全員で負担できれば良いですが、経済合理性の観点から難しいという意見もあると思います。そうした中では、木材が持つ価値として、経済価値だけではなく、環境価値や社会価値の側面をみんなが理解した上で、みんなで共同に負担していくような仕組づくりが必要だと考えています。例えば基金のようなものを創設して、川上から川下まで、事業に携わった人たちが平等に山元に必要なコストを補完し合うような仕組みができれば素晴らしいことだと思っています。
国産材と輸入材を適材適所に使う
杉田 国産材の価格については、高度経済成長に伴う需要の増大等の影響により1980年にピークを迎えた後、木材需要の低迷や輸入材の影響等を受け長期的には下落しています。近年はほぼ横ばいで推移していましたが、2021年にはウッドショックの影響によって輸入材の供給が不安定となり、国産材の需要増加に伴って価格が大きく上昇しました。2023年にかけては下落傾向にあるものの、ウッドショック前の2020年と比較するとやや高値となっているのが現状です。
隅 木材を利用する需要側の立場として、コストは経営判断に大きく関わる部分です。今後の国産材と輸入材の価格差についてはどのようにお考えでしょうか。
杉田 一般流通材に関しては、国産材と輸入材の価格差は縮まってきている傾向にあります。一方、ウクライナ情勢など、昨今の地政学的なリスクは非常に高くなっており、これにより木材価格をはじめ多方面に影響が出る可能性があります。そして、こうしたリスクは一過性のものではなく、今後も発生が予想されます。そのため、国産材と輸入材のそれぞれの特性を生かして、適材適所に使用することが重要だと考えています。
サプライチェーンが一体となって安定供給を目指す
隅 新・本店ビルの建築にあたり苦労したことの一つとして、木材の調達が挙げられます。大量の木材を使用するため、供給力の制約があり、毎月の調達量に配慮する必要があるほか、調達した木材の保管場所などについても苦労があります。今回のように、非住宅案件で大量の国産材の需要があった時、安定的に木材を供給するためにはどういったことが必要だとお考えでしょうか。
杉田 非住宅案件における木材の安定供給に向けては、サプライチェーンを短くしてコストを削減するという考えもありますが、木材調達には伐採や乾燥、加工のほか、現場に向けて届けられた木材をストックし、工程に合わせてお届けするアッセンブル機能など、様々な機能が必要となります。これらの個々の機能を整備していくことがまずは重要だと考えています。
また、非住宅案件においてCLTや大断面の集成材、LVL等が使用されるケースでは、まだまだ供給側が連携できていない現状もあります。特に大型物件では木材先行手配、木材ストック機能が不可欠な為、各ステークホルダーが連携し、全体の流れをコーディネートすることが必要です。どこか1社だけで取り組むのではなく、川上から川下までの皆さんと力を合わせながら、木材調達のネットワークを構築することが非常に重要だと考えています。
隅 本日はありがとうございました。
杉田 ありがとうございました。
※ ウッドソリューション・ネットワークは、木材利用拡大を目指す産・学・金連携のプラットフォームです。
林業生産者団体や、木の加工・流通に従事する製材会社、商社、ゼネコン、ハウスメーカー等、木に関わる約30の関連企業・団体で構成しており、農林中央金庫が事務局を務めています。