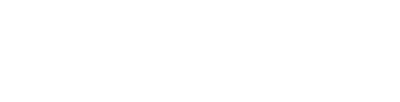ニュース&レポート
政府 地球温暖化対策計画・第7次エネルギー基本計画閣議決定 再エネ拡大で2040年度に温室効果ガス73%削減へ
エネルギー安定供給と脱炭素の同時実現を推進
政府は2月18日、次期NDC(温室効果ガス削減目標)を含む「地球温暖化対策計画」及び「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。エネルギー情勢が大きく変化する中、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に向けて一体的な取り組みが推進されます。
地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画で、2021年10月に決定された前回の計画がこのたび改定されました。同計画では、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路を着実に進めていくことで、政策の継続性や予見性を高め、脱炭素に向けた取り組みを推進するとしています。具体的な目標として、2035年度、2040年度に、温室効果ガスを2013年度比でそれぞれ60%、73%削減することが示され、次期NDCとして国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC)に提出されました。
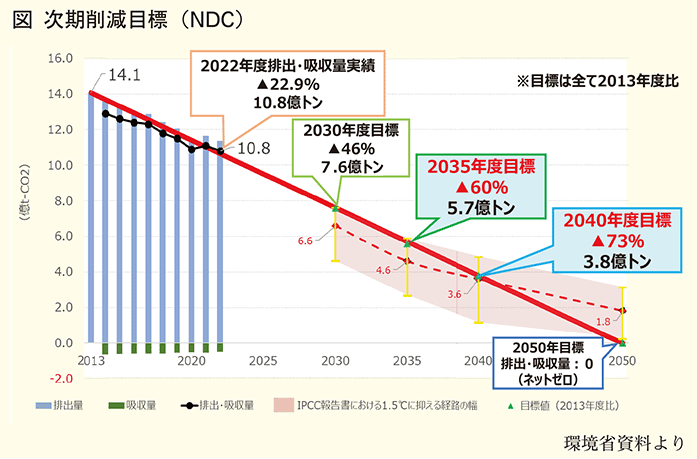
家庭部門で71~81%削減目指す
削減目標のうち家庭部門においては、二酸化炭素排出量を2040年度に2013年度比で71~81%削減することが掲げられています。住宅は一度建築されると長期ストックとなる性質上、速やかに省エネルギー性能の向上を進めることが重要であるとしています。そのため、2030年度には新築住宅で、2050年度にはストック平均でZEH水準の省エネルギー性能を確保することを目指し、省エネルギー性能の向上及び再生可能エネルギーの導入拡大を図る方針です。
また、温室効果ガス吸収源として大きな役割を果たす森林については、適切な森林の整備・保全、木材利用の取り組みを推進することで中長期的な森林吸収量の確保を図ることに加えて、他の資材から木材への転換を進めるとしています。
再エネ割合を4~5割程度へ引き上げ
第7次エネルギー計画は、新たに掲げられた2040年度温室効果ガス73%目標と整合的な形で策定されました。本計画では、DXやGXの進展による電力需要増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源を国際的に遜色のない価格で確保できるかが、日本の産業競争力に直結する状況であると述べています。そのうえで、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく方針です。
2040年度における具体的な電源構成としては、再生可能エネルギー電源を2023年度の22.9%から4~5割程度へ、原子力電源を同じく8.5%から2割程度とする方針です。また、再生可能エネルギー電源のうち太陽光発電については、2023年度の9.8%から23~29%程度まで大幅に引き上げるとしています。これにより、2023年度に68.6%を占めていた火力電源の割合を、2040年度に3~4割まで引き下げることが目指されます。