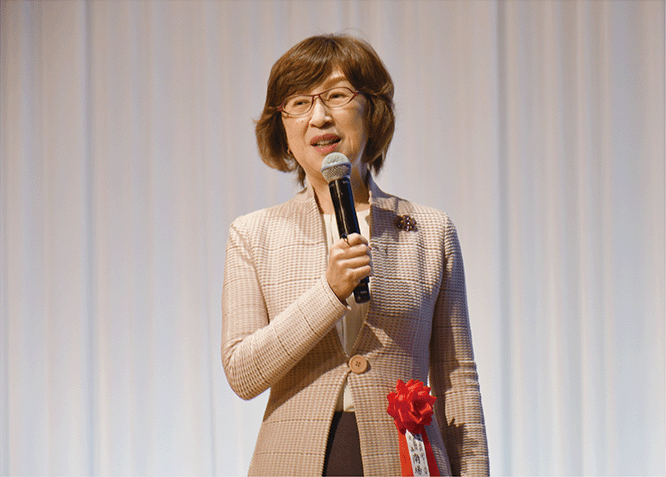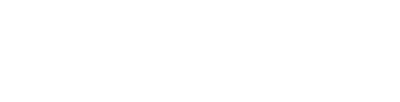ニュース&レポート
新春経済講演会 第二部特別講演 DeNAのこだわり~人、組織、ギャラクシー構想~ 株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子 氏
1月22日に開催された新春経済講演会において、「DeNAのこだわり~人、組織、ギャラクシー構想~」と題し、㈱ディー・エヌ・エー代表取締役会長の南場智子氏にご講演いただきました。講演では、社員一人ひとりが個性や情熱を発揮して成長できる環境づくりを中心に、同社の取り組みが語られました。今回は、講演要旨に加えて、講演後に行われた質疑応答セッションの内容をまとめてご紹介します。
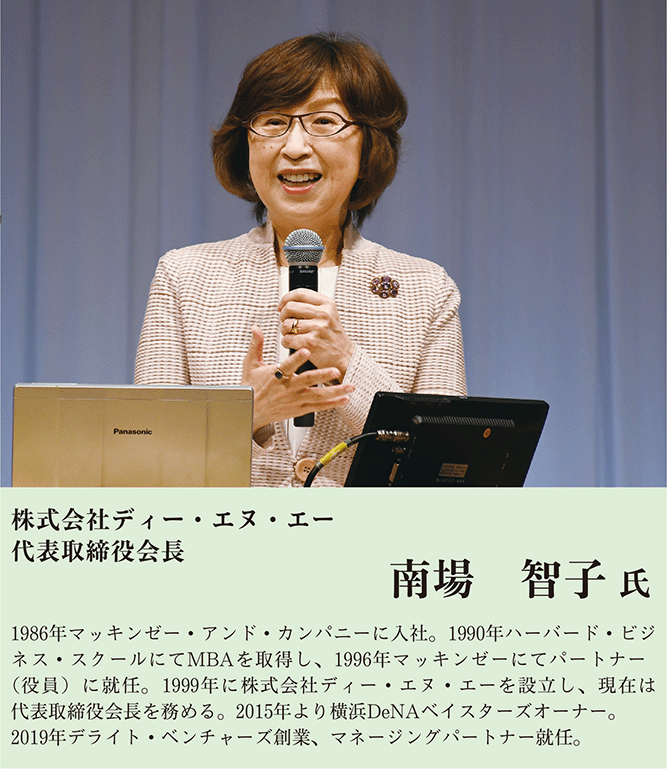
事業を通じて「Delight」の提供を目指す
DeNAの事業は多岐にわたります。最近では、スマートフォン向けゲームアプリ『Poke´mon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』が配信開始1ヶ月半で全世界累計6,000万DLを突破するなど、世界中の皆さんに楽しんでいただいております。また、リアルタイムのインタラクションを楽しめるライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」や、タクシー配車アプリ「GO(ゴー)」も、当社グループのサービスです。そのほか、ヘルスケアやメディカルの分野でも事業を展開しています。
加えて、野球チームの「横浜DeNAベイスターズ」、バスケットボールチームの「川崎ブレイブサンダース」、サッカーチームの「SC相模原」など、神奈川県のチームにこだわりを持ちながらスポーツ事業を推進しています。特に野球に関しては、球団だけではなく本拠地である横浜スタジアムについてもしっかりとオーナーシップを持って運営し、お客様に楽しんでいただくための演出、環境づくりなど様々な経営努力を行ってきました。昨年は26年ぶりに日本シリーズ優勝を経験し、これまで様々な経営努力でお届けしてきた喜びとは比較にならない大きな喜びをお届けでき、勝負事はやはり勝たなくてはいけないと改めて実感しました。なお、横浜スタジアムに隣接する地区の開発も手掛けており、今年の年末にはライブビューイングアリーナ等を備えた大規模複合商業施設が完成予定です。このように当社は、バーチャルからリアルまで、エンタメから社会課題の解決まで、多岐にわたる事業を展開しており、当社が何をやっている会社かを10人に尋ねたら、全員が異なる回答をされるかと思います。
このように多様な事業を手がける当社が唯一こだわっていることは、事業を通じて大きな「Delight」を届けるということです。「Delight」は「喜び」という意味ですが、込めているニュアンスとしては、「ここまでやってくれるのかDeNA」と表情がぱっと明るくなる、少し驚きを伴うような喜びです。当社には約3,000人の社員が在籍していますが、当社が事業を行ううえで最も大切なことは何かという問いに対して、全員が「『Delight』の提供」と答えるはずです。当社は、「Delight」を大きなインパクトで提供できるのであれば、どんな事業でもチャレンジしようという姿勢の事業創造プラットフォームなのです。
これまで手掛けてきた事業のほとんどがボトムアップ型で生み出されてきたもので、提案されたアイデアを事業化するかどうかの判断基準は三つあります。一つ目は、成功した際に提供できる「Delight」が大きいかどうかです。数億円ではなく、数十億円から数千億円のポテンシャルを持つ事業である必要があります。二つ目は、当社がやる理由があるか、勝てる理由があるか。そして三つ目は、提案してきた社員が「やりたくてしょうがない」と目を輝かせているかです。この三つを満たしていれば絶対やろうということで、次々に事業が生み出されています。
「情熱」「面白がり」を持つ人材採用が最優先
当社のようなボトムアップ型の体制の場合、右向け右と言ったら右を向くような、言われたことを忠実にこなす社員だけでは事業が生まれてきません。そのため、当社の社員として求める人材については非常に強いこだわりを持っています。
一つは、正しい答えを導き出せる能力ではなく、自分が何かを成し遂げたいという意志や情熱を持っているかどうかです。情熱がすごく分かりやすい人もいれば、あまり目立たないながらも静かに青い炎を燃やす人もいますが、どちらのスタイルであっても自分の意志をしっかり持てる人材なのかどうかを見ています。もう一つのポイントは、「面白がり」です。自分で興味を持って、深掘りしていくことができるかどうかということです。最終面接では、長い時には1週間かけて、本当にその人が「面白がり」ができるのか、苦境に立たされても折れない情熱を持っているのかを見定めていきます。当社は、一般的に高学歴と言われる大学出身の社員が多いため、一見するとエリートを多く採用していると言われることもありますが、実際の採用基準は全く違います。
私自身、採用活動には相当な時間を使っています。年間30~40回開催する会社説明会を全て自分で担当しているほか、魅力的な人材に出会ったら全力で追いかけます。残念ながら他社に入社してしまった場合でも、半年に一回は定期的に会い、その後どう成長しているのか、何が面白いと感じているのかを聞きながら、引き続き当社で一緒に仕事をしようと伝え続けます。人によっては、数年かけて勧誘し続けることもあり、当社の代表取締役社長である岡村信悟もその一人です。あるプロジェクトで総務省と一緒に仕事をした時に出会い、プロジェクトが終わってすぐに声をかけ、そこから7年間断られ続けたものの、最終的に当社に来てくれました。私にとって採用活動は、例えば大企業の社長との会食や政治家を囲んだ勉強会などよりも優先順位は数倍高く、多くの時間を充てています。年初には、今年必ず採用につなげたい方々のリストを作るくらい、人材に対してはハングリーです。その結果、当社には本当に誇らしく素晴らしい人材が揃っています。
ここまで人材にこだわるのには理由があります。トップが極めて優秀な場合は、トップの明確なビジョンやリーダーシップ、アイデアで事業が進んでいくかと思います。ただ、私の場合はそうではないということが、会社を立ち上げてすぐに分かりました。そこで、自分よりすごい人を採用し続け、彼らに中心となって事業を行ってもらうことが当社の発展に繋がると考えました。これが私の戦略となったため、人材を採用するための時間を最優先にしています。
「ストレッチアサイン」で成長を促す
入社後は、「ストレッチアサイン」によって社員の成長を促すようにしています。例えば当社では、社員にとって達成できる確率が50%程度の仕事を任せるようにしています。一つの仕事をクリアしたと思ったら、次は更に難易度の高い仕事が飛んでくるというのが当社のやり方のため、社員は結構大変だと思います。また、当社では失敗も多く起こりますが、失敗の仕方を見て、良い失敗であれば更に大きいチャンスを提供しています。成功、失敗は運にも大きく左右されますが、それを他責とせずにしっかりと自分の学びに生かしているかどうか、やるべきことを全て高いクオリティでやった上での失敗かどうかを見て、両方を満たしていれば、次は更に大きな仕事を任せるようにしています。
また、「人は仕事で育つ」という考えのもと、研修による教育は最低限にとどめ、とにかく本番の打席に立たせるようにしています。野球では本番の打席に9人しか立つことができませんが、事業では打席が無限大にあります。そのため、全員が一軍で本番の打席に立っているということを社員に伝えています。
社員全員が「球の表面積」を担っているということも共通言語になっています。当社の組織をピラミッドではなく球体型組織とし、新入社員もベテラン社員も球の表面積を担っているという考え方です(図1)。また、球は見る角度によって無数の真正面があるため、全員が誰かの真正面に立っていることになります。つまり、自分が関わっている仕事に関しては、誰かの代理ではなく、自分自身が会社を代表しているということです。
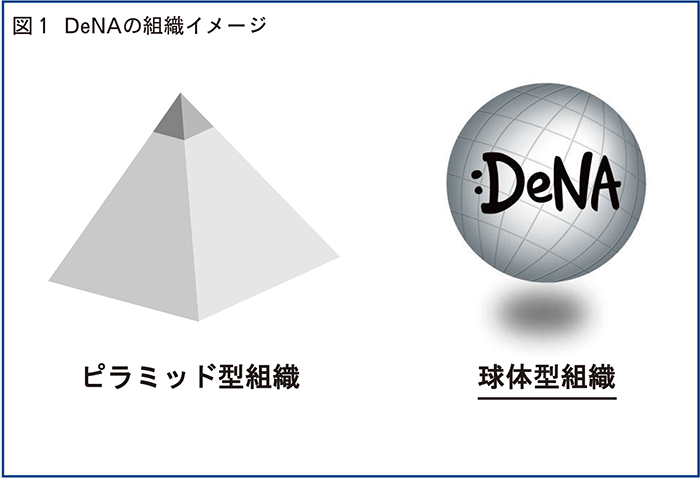
「個性と夢中」をリスペクトして強みを引き出す
「個性と夢中」という言葉も大事にしています。年に2回行っている社員の業績評価の際には、足りないことやできていないことを頑張らせるのではなく、その人の強みやカラーは何か、何に夢中になっているのかを引き出して、その個性を武器に活躍できるような環境づくりを目指しています。
そのための制度の一つとして、シェイクハンズ制度というものがあります。自分が担当する仕事に夢中になれず、自助努力しても気持ちが変わらない際は、他の事業部のフロアを見て廻り、面白いと思った事業部の本部長を見つけて話を聞き、ぜひやってみたいと思ったら自分を売り込むことができます。本部長はその人と面接し、何ができるのか、どうしてこの事業をしたいのか、これまでどんな失敗をしてきたかということを聞き、ぜひ自分の事業部に欲しいと思ったら握手をします。その瞬間に、異動が決定するのがシェイクハンズ制度です。そこから引き継ぎが始まり、早くて1週間、遅くても数か月で希望の場所で働けるこの制度は、多く活用されています。そのほか、興味のある仕事の兼務を申し出ることができるクロスジョブ制度や、起業の意向を表明できる独立起業支援プログラムを設け、社員の成長機会を提供しています。
また当社では、ヒエラルキー、すなわち階層で仕事をしません。例えば、社内でよく言われる言葉に「誰が言ったかではなく何を言ったかが大事」というものがあります。会長や社長が言ったから、本部長の意見だからというように、物事を進める際の根拠を「人」に求めることをする社員はほとんどいません。
これに近いものとして、思考の独立性も重視しています。例えば、私が参加するミーティングにおいて議論が行われる中で、常に私と同じ意見の人はいずれミーティングに呼ばれなくなります。自分の考えを持ち、異なる意見を述べられることを当社では必須としているため、私や社長が進めたい事業について議論している時に、「それは違うと思います」と言われることも少なくありません。自分の独断で会社を間違った方向に導かないためにも、社員の言うことにしっかり耳を傾けていますし、そのためにリスペクトできる社員を集めているのです。
また、ヒエラルキーで仕事をしないことの証左として、グループリーダーや課長、部長、本部長などの役職が給与と結び付いていません。そのため、高度な研究を行っているAIの研究者や、ユーザーインターフェースのプロフェッショナルの社員が、社長よりも高い給与を得ているケースもあります。彼らのような高い専門性の価値が、マネジメントの価値に劣るということはないと考えています。
最も大切な心構え「ことに向かう」
事業において一番大事にしていることは「Delightの提供」ですが、社員の心構えとして重視しているのが「ことに向かう」ことです。これは、本質的な価値を提供することに集中するということです。誰かの機嫌、自分の立場、椅子の取り合いなど、仕事では多くの誘惑があり、常に「ことに向かう」ことはなかなか難しいことです。例えば、社員と一対一で議論する際、お互いにヒートアップして激論になることがあります。その時、けんかっ早い私は、どういう言葉が相手にダメージを与えられるかを考えて、その言葉をぶつけてしまうこともあります。この時、「今、私は喧嘩に勝つことに向かっていないか」ということに気づき、改めて「ことに向かおう」と相手に問いかけます。この言葉によって相手も正気に戻り、会社や事業の成功のために何がベストかを考えるようになります。このように、議論の最中にも自分を客観視できるのは、日頃から社員同士で「ことに向かう」という言葉を言い合っているからです。様々な個性がある当社の中で、決して譲れないものがこの言葉です。
社員を囲い込まない「DeNAギャラクシー」
社員を囲い込まないということも、当社の特長の一つです。入社した後、事業リーダーやスペシャリストとして社内でステップアップする人もいますが、「独立起業・スピンアウト」というキャリアパス制度も設けています。この制度によって、当社を卒業して新たに起業することを、会社として公式に応援しています。社員を閉じ込めるのではなく、とにかく開放するという考え方で、新しい事業をするために会社の外に出ていくことがあっても良いと思っています。やりたいことを実現するために、自分にとってベストな場所を選択してもらうということです。
これを夜空に例えると、当社を卒業して自分の星をつくっている人がたくさんいます。そうした方々とこれまでも個人的なつながりは持っていましたが、当社としてもできる限り出資してつながりを持つことで、Delightの総和を最大化する仕組みを作りました。しかし、考えてみれば、「ことに向かう」を実践する素晴らしい姿勢を持つ人は、当社のOB・OGに限らず様々なところにいらっしゃいます。この方々を除外することなく同様に出資することを目的に、デライト・ベンチャーズという独立系のベンチャーキャピタルを設立しました。「起業家ファースト」「スピーディーな決断」「目先の利益<将来の価値」「失敗こそプレミアム」「世界基準」の五つの約束を設定し、起業家を支え、大きな事業を輩出することに取り組んでいます。
こうした考え方を、「DeNAギャラクシー」と呼んでいます(図2)。もちろん、当社が最も事業をつくりやすく、育てやすい場所であるために努力し続けますが、当社よりも更に良いステージを見つけたら、そこで活躍することを応援するように徹底しています。
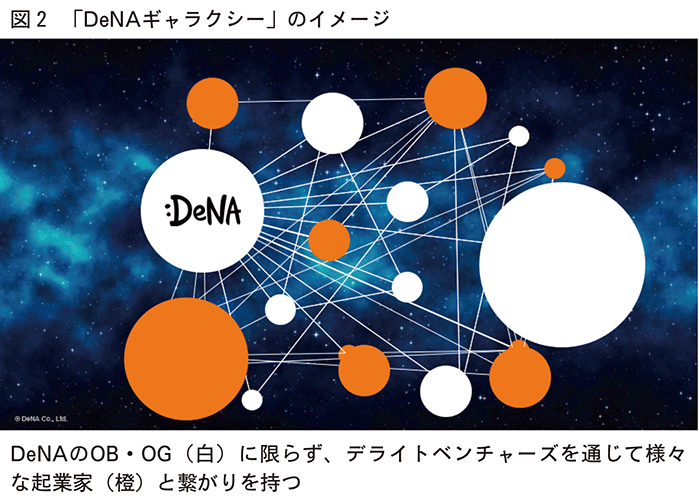
チェンジエージェントとしてのDeNA
近年、日本企業の企業価値は低迷しています。2024年3月時点の企業価値上位10社の企業を見ると、米国と比較して企業価値の総額に10倍近く差があるほか、ベンチャーキャピタルによってサポートされた企業は日本にはありません。更に、10社のうち1990年以降に設立した企業の数は、米国が5社なのに対して日本は0社です。ダイナミズムのある経済においては、ある時代に新しい企業群が生まれ、次の時代にそれを超える企業群が生まれるということが繰り返されますが、日本では同じ企業がトップに居続けています。このダイナミズムのなさが、日本経済の停滞を招いていると思っています。
加えて、人材の課題もあります。日本企業の従業員エンゲージメントは諸外国と比べ最低基準であるほか、生産性や給与への満足度も低いというデータがあります。一方で、転職や独立・起業志向がある人も少なく、社外学習・自己啓発を行っている人の割合が低いことも明らかになっています。つまり、日本の従業員は「覇気がない」と言えます。
また、リーダーに着目すると、世界には、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、イーロン・マスクのような、強いこだわりや並外れた行動力を持つ、傑出したグローバルリーダーがいます。彼らは稀なケースですが、欧米におけるリーダー像のように、自分の考えを持ち、パッションを表現でき、異なる背景の人たちと協調して束ねられるリーダーを輩出できる国にならなければいけないと考えています。日本で優れたリーダーが生まれない最大の課題は、教育システムにあると考えています。均一的な集団の中で、一律の内容を一律のペースで受動的に学ぶ日本の教育では、リーダーを生み出すことは難しいと思います。
当社では、「スタートアップ不足」「人材」という二つの課題解決に取り組んでいきたいと考えています。「スタートアップ不足」に関しては、当社が更に成長し続けるのはもちろんのこと、当社で仕事の基礎を学んだ方々が自らスタートアップを立ち上げ、ユニコーン企業に成長させ、世界で活躍していくことを大いにサポートしていきたいと思います。また、「人材」については、当社にいることで事業を生み出す力を身につけるとともに、自分の頭で考える訓練を受けた人材を輩出していきます。これらによって、日本の課題に対応し、チェンジエージェントとしてのDeNAを目指していきます。
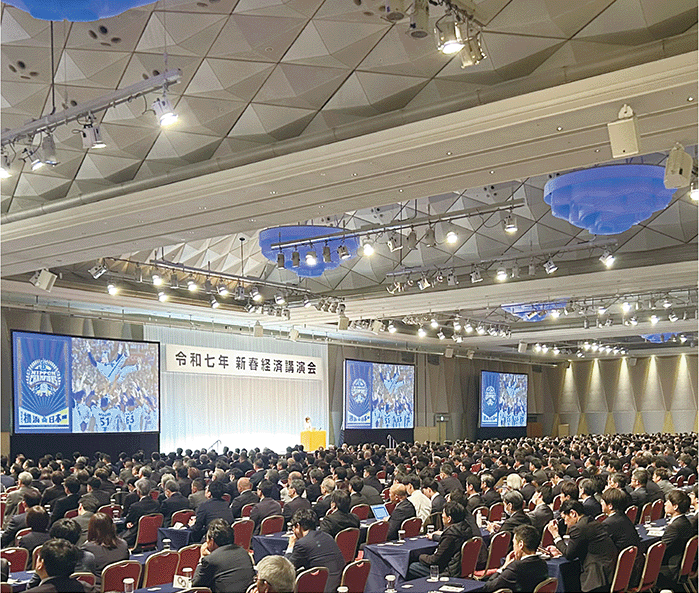
質疑応答セッション
講演の後、ライブでの質疑応答セッションが行われました。会場内では多くの来場者の挙手があり、個々の質問に対して南場氏より回答がなされました。その一部をご紹介します。
―社員から、モチベーションの低下などを理由に退職の申し出があった場合、どのように対応されるのか教えていただけますか。
南場 当社の場合、次にやりたいことがあるなど前向きな退職については引き止めませんが、ネガティブな理由で退職の意向が出てきた際にはとことん話すようにしています。そのうえで、その方の得意なことや個性が生かせる場所を提供し、異動後も丁寧にフォローしています。多角的に様々な事業を手掛けているからこそ、今はモチベーションが下がっていても、きっとその方の個性を生かして輝ける場所があるはずだという思いで対応しています。
―ご自身より優れた人材を採用し、その方々によって事業を推進していくというお話がありましたが、その考え方に至ったきっかけや経緯などがあれば教えていただけますか。
南場 きっかけは、失敗やつまずきなどの経験です。私はエンジニアではありませんから、プログラミング言語を使ってソースコードを書くことも不慣れで、大きな失敗をしてしまったことがありました。資金調達における資本構成でも失敗がありました。また、サイトのデザインについて自分なりに相当勉強したつもりでも、プロのデザイナーの加入によってクオリティが格段に上がり、ユーザーの満足度が高くなったこともありました。こうした経験から、専門家やその領域のプロの方々に仲間になっていただき、達成したいイメージを共有して任せていくという形になっていきました。だからこそ、優秀な人材の採用が当社にとっての最優先事項なのです。
―日本と米国の教育の違いに関するお話がありました。社会人になってから、どのような機会があるとグローバルリーダーに近い人材を育成できるとお考えでしょうか。
南場 当社も日本人が多いので、ふとした瞬間に「正解」を求めてしまうなど、日本教育のハンディキャップを感じる場面はあります。成長するために最も必要なことは、成功体験だと考えています。私の意向を気にすることなく、自分の考えに沿って行動し、成功して祝福されるという体験です。ただし、あまり簡単な成功体験では意味がありません。難易度の高いミッションに挑戦し、苦しんで悩んだ結果としてつかんだ成功体験は、人を大きく成長させると思います。期待して採用したのに伸び悩んでいる社員がいれば、成功確率50%程度の仕事を任せてみて、成功するまで頑張ってもらいたいという気持ちで見守っています。
―役職と給与が結びついていないというお話がありましたが、具体的な制度の内容や運用上のコツなどがあれば教えていただけますか。
南場 具体的な事例を挙げますと、とてもクリエイティブでトレンドに対するアンテナも高い優秀な広報担当者がおります。この社員は、マネジメントには全く関心がないため、役職を持っていませんが、給与水準は非常に高いです。これは、役職とは別に、給与に結びつくランク制度を設けているからです。どれだけ自立的に企画ができるのか、得意な分野におけるマーケットバリューはどの程度なのかなど、いくつかの要素によってランクを決める仕組みとなっています。専門性の価値を重視している当社ならではの制度だと思います。